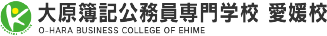こんにちは。公務員系学科の学科長、小松でございます。
4月ですね。当たり前ですが大原にも新入生が入学し、新年度がスタートしています。
3月に卒業した大原生たちは仕事頑張ってますか??
ニュースになってますが、3日で「も~〇り」とか退職依頼しないでくださいよ^^
さてさて、我が公務員専攻科は4月に入学し、半年後には公務員試験を受験するというハードな学科ですが、今年もまた昨年に輪をかけて「お勉強苦手学生」ばかりとなっております。
私はここ数年、新入生に対して「君たちは本当の意味では小学校を「卒業」していない」と言います。
私には中学校3年の娘とこの春中学校1年になる息子がいますので、小学校の勉強が何たるかは分かっているつもりです。
小学校での学びは本当に大切です。受験とか関係ないです。
生きてく上で重要というレベルだと思います。
持論として、「18越えたら性格なんか変わらんわい」というのがありますが、社交的かどうか、能動的か受動的かなんて言う性格はほとんど小学校時代に決まると考えています。親や家庭の影響は当然ありますが、小学校がどうだったかという点がすごく大きなウエイトを占めると思っています。
と、この場を借りてお礼を申し上げておきます。
松山市立姫山小学校の先生方、うちの二人の都合8年間、本当にお世話になりました。
おバカなりに、人並みの気遣いとコミュニケーション能力、自分で考えることができる基礎学力を身につけさせていただきました。
ありがとうございました!!
さて、少しそれましたが、私は小学校6年間の教育は、花壇に例えればひたすら土を肥やすことだと考えています。6年の間に花なんか咲いたらよっぽどの神童で、普通は何をやりたいか、何に興味が向くのか、何が得意で、何が不得意か、そんなことも全く分からないままに終わるのだろうと思います。
国語、算数、理科、社会に今は英語もですか。小学校で学ぶ内容は本当に多岐にわたります。
それらの知識を得ることでどうなるんだ??って思いますよね?
僕が考えるその回答は、
まず、
⓵日本人として目にしまくる、日本に出回る文章が正確に理解できるようになる。
日本語を話す、理解するには「国語」という教科だけをやればよいわけではありません。文法や漢字を学ぶことは大切ですが、それ以外の教科を学ぶことも世界屈指の難易度を誇る日本語理解には欠かせません。算数も論理的思考という意味で日本語に関わっていると思います。
次に、
⓶ある事柄を「分かる」、「知る」ことに対して「嬉しさや楽しさ」を感じることができるようになる。
最近アニメ化もされた「チ。」というタイトル1文字のマンガがありますが、読んだことありますか?
このマンガは、「知る」ということ、「考える」ということに関する自由が制限されていた、中世ヨーロッパをモチーフに描かれています。歴史的背景を知らない方も知っている方も楽しめるマンガです。
たぶん…、知らんけど…^^
日本は周辺の危なっかしい国々とは違い、「知っても良い」国です。
生まれた時から当たり前すぎて意識したことが無いかもしれませんが、「知ること」が罪にはならない国なんですよ。「知」を基本に、私たちの国は様々な「選択」について自由を認めています。
知ることは楽しいこと。私はこれを小学校で教わったと勝手に思っています。
小学校で「知るための基本」を学び、中学、高校と自身がより知りたい事柄を「選んでいく」。
そうやって進んでいく中である知識について知り、「楽しい」と感じるものを私は「適性」と呼ぶのではないのかなと思っています。
そしていつか見極めた自分の適性を仕事にすることを認めている国に、幸い私たちは生まれています。
それを当たり前、というか考えたことも無い学生に対して、
「ボ~~~~っと生きてんじゃね~よ!」とチコちゃん風に言うようにしています^^
そして、
⓷自分の適性を見つけ、その先に将来の職業を見つけ、その職業に就くための力になる。
カッコいいことを書いてしまいましたが要は、「好きだ」、「やりたい」、「なりたい」と言ってもその力が自分に無ければその選択肢を取ることは出来ないということです。
例えば私なら、予備校の世界史の先生になりたいと大学浪人中に思ったわけですが、
そのためにはまず「高校教諭(地理・歴史)の教員免許」が必要で、その免許を取得するためには大学に行く必要があり、大学に行くためには勉強をして入試に勝つ必要があり、勝つ力(偏差値)を高めるには予備校に言って頑張るしかない・・・。ってな具合です。
先述したように、そもそも「歴史が好きだ、楽しい」とか、「人に何かを教えるのも好きだ」とか、「人と話をするのが好きだ」とか、「笑わせることが得意だ」とかは全部小学校の生活の中で自覚したものだと思います。でも、その後中学、高校が僕と同じ子達がいたとしても、皆が歴史教員を目指したわけではないですよね?
だからこそ思うんですよ、私は当時決してガリガリ勉強するタイプではなかったですが、小学校の勉強をする中で、先生やクラスメイトと関わる中で、「考える」ことが出来るようにはなったのだろうと・・・。
私はこれまで18歳付近の若者2000人以上に関わってきました。
最近感じることは、残念ながら「考えない(考えようとしない)学生」が増えてきたことです。
公務員を育てる仕事をする身として、教育者の端くれとして何とかせんといかんとずっと思っています。
公務員に合格しさえすりゃ良いとは思っていません。
だから学生には言います。「もう一度、今度はちゃんと小学校を卒業しよう!」
国語や算数の学び直しも重要だけど、挨拶や返事など当時できていたけど今はできなくなったことをちゃんとやろう、と。
僕が公務員専攻科で1年かけてやろうとしている教育は、全国の大原で共通の公務員試験対策は当然ですが、この学び直しを通して「考えることができる公務員を育てること」です。
あかん、なんぼでも書けてまう・・・。
今日はこれくらいにしといてやろう^^